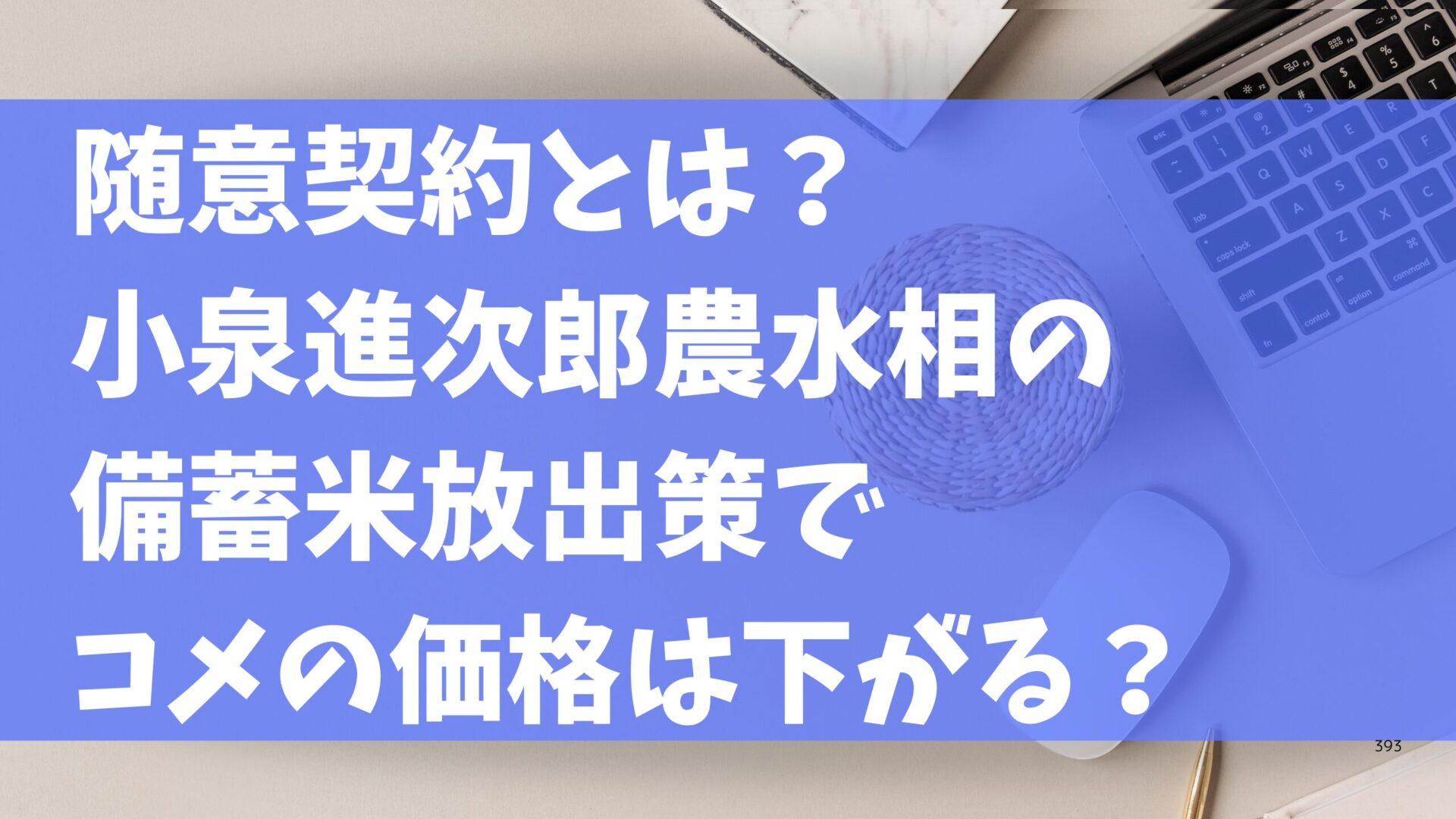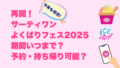コメの価格が2倍以上に高騰している今、農水相に就任したばかりの小泉進次郎さんが「備蓄米を無制限に出す」と発言して話題になっています。
しかも、その売り方を「随意契約に変えるかも」とのこと。
…えっ、随意契約ってなに?どういう意味?
「たくさん出せば値段が下がるってこと?」
「無制限って、そんなに米が余ってるの?」
「中間業者はどうなるの?」
――そんな素朴な疑問を持つ方に向けて、小泉さんの発言の意味、そして「随意契約ってそもそも何か?」をやさしく解説します。
小泉進次郎農水相が「備蓄米を無制限に放出」
農相に小泉進次郎氏、首相が表明 随意契約で備蓄米売り渡し検討指示https://t.co/1QMRPw7hzH
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) May 21, 2025
今、日本でお米の値段がぐんと上がっています。スーパーで5キロのお米が4,000円を超えることもあり、「高すぎる!」と感じる人も多いはず。
そんな中、農林水産大臣に就任した小泉進次郎さんが、「政府の備蓄米を、必要があれば無制限に出す」と発言し、注目を集めています。さらに、「売り方も見直して、競争入札じゃなく“随意契約”にするかも」とも言いました。
でも、ここでひとつ疑問が。

無制限って本当にできるの?
ていうか、コメの「随意契約」ってなに?
というわけで、このニュースのポイントをやさしく解説していきます!
そもそも「随意契約」ってなに?簡単に解説!
「随意契約(ずいいけいやく)」という言葉、あまり聞きなれないですよね。実はこれ、国や自治体が何かを買ったり売ったりするときの“契約方法”のひとつです。
ふつうは「競争入札」といって、複数の業者が「うちはこの値段でやります!」と手を挙げて、一番安いところや条件の良いところと契約します。
でも「随意契約」は、その手続きをせずに、特定の相手と直接話して決めるやり方です。

たとえば、急に災害が起きたときに、すぐ水や食料を届ける必要がある。 そんなときにいちいち入札なんてしてられない!ってこと、ありますよね。
そういう「緊急時」や「特定の業者しかできないこと」の場合に、随意契約が使われることが多いんです。
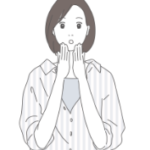
つまり、小泉農水相は、コメ価格の高騰を“今すぐ何とかしなければいけない緊急時”と捉えたからこそ、通常の入札手続きではなく、スピード重視の「随意契約」を検討していると考えられます。
随意契約のメリット・デメリットは?
ここで「随意契約って便利そう!」と思った方も多いかもしれません。たしかに、メリットも大きいです。でもデメリットもあるんです。
◎メリット
- 契約までのスピードが速い(入札不要)
- 必要な相手と柔軟に取引できる
- 緊急時に即対応できる
- 中間業者を減らせる=価格が下がる可能性も
✖デメリット
- 価格の透明性が下がる(高くても気づかれにくい)
- 不正な取引や癒着が起きやすい
- 市場の公平性に欠ける場合もある

つまり、“素早くて便利”だけど、“公平さや透明性”が少し心配な面もある、ということです。
この制度をどう使うかがとても大事なんですね。
備蓄米を随意契約で出すと、何が変わるの?
いまは、備蓄してあるお米を売るときも「競争入札」で、高い値段を出した業者に売られています。
でもこれだと、「高く買える業者=大手」が有利になって、 その先のスーパーや消費者の手に届くまでに、どうしても高くなっちゃうんです。
小泉農水相が言っている「随意契約」に変われば、政府が「この人(この会社)に売ろう」と決められるので、 もっと早く、もっと安く、お米を市場に出せる可能性があるんです。
つまり、間に入る“中間業者”が減る=値段が下がるかも?という期待です。
ただし、先ほどのデメリットもあるので、「どんな相手に」「どんな条件で」売るのかが重要になってきます。
小泉発言の波紋…JAなどとの関係に影響は?
今回の「随意契約への切り替え」や「無制限放出」という発言は、業界関係者にとってインパクトが大きく、一部では不安の声もあがっています。
たとえば、備蓄米の入札では、これまでJA全農がほとんどを落札してきました。しかし、小泉さんは入札を中止し、スーパーなど幅広い業者に“直接売り渡す可能性”を示しています。
これは「JAを通さずに販売する」という意味合いも含んでおり、JAや既存の流通ルートとの関係に亀裂が生じる恐れも。

一部では「小泉さん、また業界の反発を招くのでは?」という声も出ています。
もちろん、目的は“価格を下げて消費者を助けること”です。でも、その手段が関係者の理解を得られるかどうかは、今後の丁寧な説明と制度設計にかかっているといえるでしょう。
「無制限に放出」は本当に可能?備蓄米の在庫量と過去の放出例
「無制限に出す」と聞くと、「そんなに米があるの!?」と思いますよね。
実際、政府が持っている備蓄米は約91万トンありました。 すでに3月〜4月にかけて31万トンほど放出されていて、今残っているのはおよそ60万トンです。
計画では「1か月10万トンずつ出す予定」でしたが、それを超えて“ドーン”と出すかもしれない、という話になっているわけです。
ただし、「無制限」とはいえ限界はあります。 しかも、一気に出しすぎると市場が混乱してしまうリスクも。

お米が余ってるように見えたら、農家さんが困っちゃう…という側面もあるのです。
ネットの反応と専門家の声は?
SNSではすでに賛否両論です。
- なぜ随意?普通の入札で良いのでは? 前回の入札はなぜか予定価格近似落札ではなく、競売(高値落札)だったし。
- いやいや、一気に備蓄米を放出するだけで、米不足と米高騰はある程度解決しますよ
- 何故に随意契約??
- 随意契約ね。利権が絡んでそうな気がするな。
- まだ何も始まってないからね。賛否は結果を見た後だね。
- 入札制度じゃ価格は下がらないって散々言われてたしこれは英断かな
- じゃあなんで江藤はこれをしなかったのか これまでも出来レースに見える
株と一緒で、政府が本気を出したら市場価格は動くので、高値狙いの中間業者は早く手放さないとドンドン安くなる。
— ひろゆき (@hirox246) May 21, 2025
アナウンス効果としても、小泉進次郎さんはアホみたいな量を出して関係者の度肝を抜く天然っぷりを発揮しそう。
〉小泉農相 備蓄米放出「無制限に」
https://t.co/6crQKp9yO6
ひろゆきさんのXの投稿では、そもそもの根本の原因を指摘しており、いずれにしても「ただ出せばOK」ではない複雑な背景があるのは確かです。
なお、ひろゆき氏は21日の投稿で「米価格問題は、根本的には、燃料費、肥料代、殺虫剤、除草剤、委託人件費が上昇してるから価格も上がるわけです」と書き出し、「ほかの農作物や漁業でも同じ事が起きてます。日本人労働者の手取りを増やし5kg5000円の米でも普通に買える社会にすべきなのですが、小手先の政策で解消すると誤解してる人が多い」と述べていた。
まとめ|随意契約と“無制限放出”で米価は下がる?今後の注目点
・随意契約は、特定の相手と直接契約できる制度で、スピードや柔軟性がメリット ・でも、透明性や公平性には注意が必要 ・備蓄米の放出量はまだ余力があるが、“無制限”は言いすぎかも ・中間業者を減らせば、私たちの買うお米も安くなる可能性はある ・JAなど既存流通との関係性に変化が出る可能性も
小泉さんの“大胆発言”が、今後どんな政策につながるのか。 そして実際にお米の価格がどう動くのか、引き続き注目ですね!