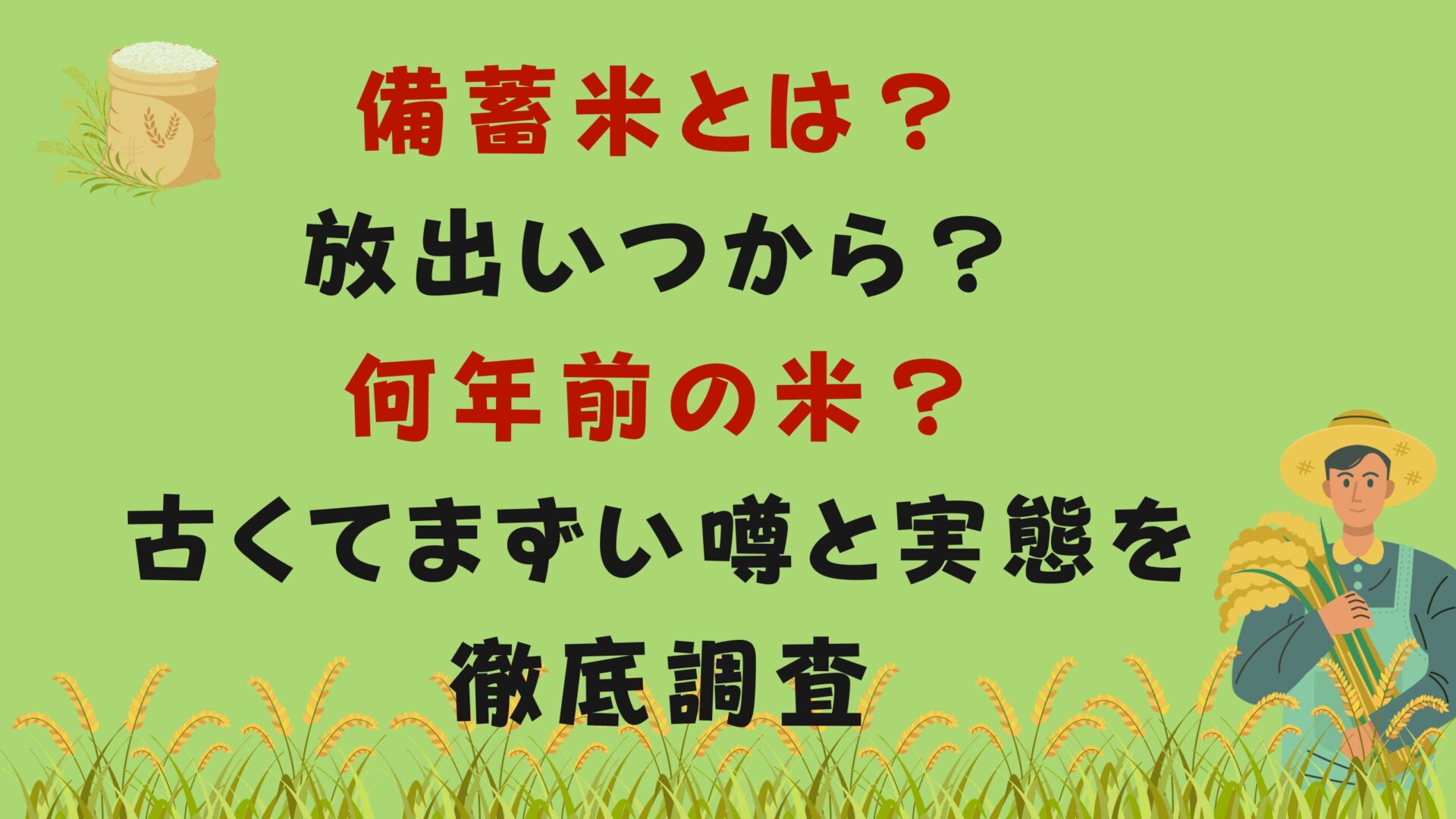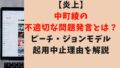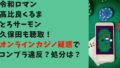2025年2月の江藤農水相による備蓄米放出の表明以降、政府の対応は大きく動きました。江藤氏の失言による更迭を受け、小泉進次郎新農水相のもとで方針がスピーディーに転換され、備蓄米は入札方式から“随意契約方式”へと変更。
これにより、イオンやファミリーマートなどの民間企業が政府から備蓄米を直接購入し、6月以降、全国の店頭やネットで販売されることになりました。
いわば「令和の米騒動」とも言える状況下で、急速に市場へと流れ始めた備蓄米。
一方で「備蓄米って古くてまずいんじゃない?」「何年前のお米が放出されるの?」と不安に感じている人も少なくありません。
この記事では、そうした疑問に応えるべく、そもそも備蓄米とは何か?放出の仕組みや味・品質の実態、そして放出による市場への影響まで、わかりやすく徹底解説します。
備蓄米とは?
【会見】政府、備蓄米21万トン放出と表明 3月初めに入札開始へhttps://t.co/ZRBQmivWGM
— ライブドアニュース (@livedoornews) February 14, 2025
備蓄米の放出は、集荷業者に対して行う。農水省は入札で選んだ業者に売却し、過度に米価が下落することを防ぐため、1年後をめどに同じ業者から同量を買い戻すという。 pic.twitter.com/gvnzUpVQPc

この制度は、1995年に法律として制度化され、1993年の大凶作を受けて設立されました。

備蓄米の目的は大きく2つ
- 国民が安定して米を食べられるようにすること
- 米の市場価格を安定させること

今回はこの2番、米の市場価格を安定させることが目的ということになります。とはいえ、コメの流通の円滑化を目的に政府が備蓄米を放出するのは初めてだそうです。
備蓄米放出の背景は?
行方不明米と言われる存在です。
去年2024年の生産量は前年比約18万トン増量したにもかかわらず、去年末の集荷量は前年比約21万トン減少している。お茶碗約32億杯分が行方不明!
ここから米の流通が滞り、高騰を招いていることが備蓄米放出に至る背景になります。
備蓄米の放出はいつから?
政府の発表によると、備蓄米の放出スケジュールは以下の通りです。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2025年2月14日 | 備蓄米21万トンの放出決定(第1回は15万トン) |
| 2025年3月初旬 | 入札公告実施 |
| 2025年3月中旬 | 集荷業者への引き渡し |
| 2025年4月以降 | 小売店での販売開始 |
| 2025年5月中旬 | 江藤拓農林水産大臣が失言で辞任 |
| 2025年5月 | 小泉進次郎氏が新農水相に。随意契約検討発言 |
| 2025年5月26日 | 随意契約申請受け付けを開始 |

つまり、消費者のもとに届くのは3月中旬以降、早ければ4月頃と言われていましたが、実際消費者としては実感があまりない状況でした。
江藤大臣の辞任。小泉進次郎氏が農水相を担当すると随意契約で6月にはスーパーなどの店頭で並ぶ見込み。
備蓄米を放出するとは具体的に?
年間の玄米仕入れ量が5千トン以上の大手集荷業者に対して行う。農水省は事業者を入札で選び、原則1年以内に同じ事業者から同量を買い戻す。
引用元:ライブドアニュース

過度に米価が下落することを防ぐため、ということのようです。
備蓄米 何年前のお米が放出される?
政府備蓄米
— 吉之輔 (@bakutora_kojiro) February 7, 2025
何年前の米出してくるんやろ。
運んだ事あるけど…#備蓄米
春に放出された15万トンの備蓄米の内訳は以下の通りです。
- 2024年産米:10万トン(昨年収穫された新しいお米)
- 2023年産米:5万トン(1年以上前に収穫されたお米)
つまり、春に放出されたお米の大半(約67%)は2024年産で比較的新しく、古米と呼ばれるのは2023年産の5万トンのみ。
今回2025年5月に小泉進次郎農林水産大臣のもとで導入された備蓄米の随意契約制度により、販売されるお米の産年は以下の通りです。
- 2022年産(令和4年産):20万トン
- 2021年産(令和3年産):10万トン
これらは合計30万トンで、いずれも政府が保管していた古米にあたります。特に2021年産は収穫から4年が経過しており、「古古米」とも呼ばれます。これらの備蓄米は、これまでの競争入札方式ではなく、政府が定めた価格で大手小売業者と直接契約する「随意契約」によって販売されます。
販売価格は、
2022年産が60kgあたり税抜き10,010円
2021年産が10,080円
平均すると10,700円となります。これを一般的なマージンを加味して小売価格に換算すると、5kgあたり税込みで約2,160円程度になると見込まれています。
この新たな制度により、ファミリーマートや楽天などの大手小売業者が政府備蓄米の販売に参入し、早ければ6月上旬から全国の店舗やオンラインでの販売が開始される予定です。
古くてまずい?備蓄米の品質と味
政府備蓄米っておいしいのかな?どんなに管理してるっても4年前の米だけど
— せら (@k_sera_sera) January 24, 2025
実家農家で、納屋で保管してた古古古米みたいなんはまずかった
もしおいしくなかったらわすはきっと新米を買ってしまう
自分でまずいと感じた米を食い続けるのは苦痛なのだ🙄
「備蓄米は古いからまずいのでは?」という懸念について、実際の保管状況や味への影響を調査しました。
備蓄米の保管方法
- 備蓄米は玄米の状態で低温保管されており、精米後の米よりも味の劣化が少ない。
- 害虫やカビの発生を防ぐため、厳格な管理のもとで保存されている。
古米でも美味しく食べる方法
もし購入した備蓄米が古米だった場合、以下のポイントを押さえることで美味しく炊くことができます。
✅ 研ぎすぎない(米の表面を削りすぎると風味が損なわれる)
✅ 30分以上しっかり浸水させる
✅ 炊飯時に酒やみりんを加える(米1合に対し小さじ1〜2)
✅ 炊飯後にしっかり蒸らす
これらを実践すれば、備蓄米でも美味しく食べることができます。
備蓄米制度とは?
備蓄米制度とは、日本政府が食料安全保障のために米を一定量保管している制度です。
| 項目 | 内容 |
| 目的 | 災害や不作時の食料供給の安定化 |
| 保管量 | 約100万トン(10年に1度の大不作に対応可能) |
| 買入れ量 | 毎年約20万トン |
| 保管期間 | 最大5年(経過後は飼料用米などに転用) |
備蓄米の放出は、通常は災害や米不足時に限られますが、今回は価格高騰対策として異例の措置となりました。
今後の米価格への影響は?
政府は「放出後に買い戻しを行う」としており、供給過多による価格暴落を防ぐ方針です。しかし、市場への影響は以下のように予想されます。
📉 短期的には米の価格が下がる可能性(供給増加のため)
📈 長期的には価格が安定(政府の買い戻しによる調整)
今後の米の価格動向を注視しながら、賢く購入するのが良いでしょう。
備蓄米を放出することのメリットとデメリット
メリット
デメリット
まとめ
✔ 備蓄米の放出は3月中旬から順次開始
✔ 第一弾は2024年産米(10万トン)が中心で、2023年産米(5万トン)のみが古米
第二弾の6月以降は2022年産(令和4年産)20万トン2021年産(令和3年産)10万トン
✔ 低温保存された玄米のため、品質は保持されている
✔ 古米でも適切な炊き方で美味しく食べられる
✔ 米価格は短期的に下がる可能性あり、今後の動向に注目
備蓄米の放出は家計にとって朗報ですが、農家の収入が圧迫され、特にコスト上昇分を賄えなくなるリスクもあり、長期的にみると手放しで迎え入れる対策ではない一面も浮き彫りになっています。購入の際は産地や保管状況を確認し、賢く選びましょう!