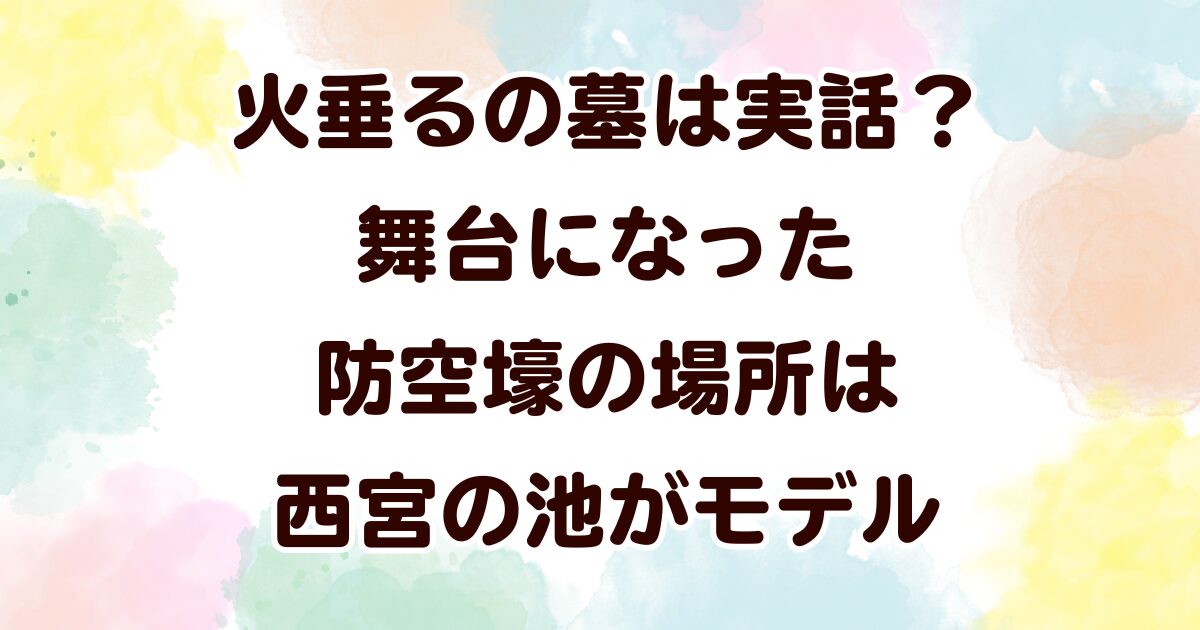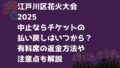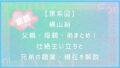『火垂るの墓』は実話が元になっていると言われています。物語の中で清太と節子が暮らした防空壕は、兵庫県西宮市の池の近くがモデルとされています。本記事では、原作者・野坂昭如の実体験や、防空壕の実在場所、アニメ版で描かれた背景との違いを解説します。また、現地で進められている記念碑計画や、今では残っていない防空壕の当時の様子についても紹介します。
結論まとめ(最初にサクッと要点)
『火垂るの墓』はどこまで実話?
原作者・野坂昭如は、1945年の神戸大空襲で義母を亡くし、義理の妹とともに親戚宅に身を寄せたのち、防空壕で暮らす生活を送りました。この実体験が物語の骨格になっています。
ただし、作品の全てが史実通りではありません。人物の言動や出来事の細部は脚色され、文学作品としての演出が加えられています。
舞台のモデル:西宮の「池」周辺(= ニテコ池)
舞台となったのは、西宮市満池谷町にある貯水池、通称「ニテコ池」。作中では、清太と節子が池のほとりで暮らす姿が印象的に描かれます。
【終戦80年】『火垂るの墓』きょう15日よる9時より「金ロー」にて放送https://t.co/pjUIO90x4A
— ライブドアニュース (@livedoornews) August 14, 2025
戦争末期から戦後の混乱期を14歳の少年・清太と、4歳の少女・節子が精いっぱいに生きる姿を描いた物語。当時の神戸の町や人々の様子、B29による爆撃の恐ろしさなどがリアルに描かれている。 pic.twitter.com/f4yJiHovyS
地元では「ニテコ池」と呼ばれますが、地図や資料では別名称で表記される場合もあります。現在も池は残っていますが、防空壕や戦時中の施設は残っていません。
ニテコ池の、この形の取水塔。火垂るの墓の防空壕のとこ。 https://t.co/KjcHbhw8G7 pic.twitter.com/xV770rAyzF
— crazytrain.ink🚑🎸📈 🎒 #REVA (@crazytrain0111) December 16, 2024
- 〒662-0031 兵庫県西宮市満池谷町11
- ニテコ池(西宮市満池谷町)の最寄り駅は、阪急電鉄 神戸本線「夙川駅」
- 夙川駅から徒歩:およそ15分前後
- もう少し近いのは阪急甲陽線「苦楽園口駅」で、徒歩約10分ほど
- JRだとさくら夙川駅からもアクセス可能ですが、徒歩だと20分近くかかります
モデルになった防空壕は2種類
火垂るの墓
— 🌸だいき@星党 (@maruYoda_YDB) August 15, 2025
清太と節子が過ごした防空壕の中で蛍を放つこのシーン、引き画になった時に木の枠で遺影になってる話聞いた時は本当に鳥肌立った
金ロー始まるまでに風呂済ませておこう pic.twitter.com/jhY7SlU1XF
地元の証言や調査によれば、モデルは2種類の防空壕とされています。
- 高射砲部隊が掘った土壁壕
池の南側斜面に掘られた横穴式で、土壁がむき出しの構造。戦時中、軍の施設として使われていました。 - 民家(社長宅)のコンクリート壕
金属加工会社の社長宅に造られたコンクリート製の壕。社長一家は疎開しており、空き家だったため兄妹が生活の場として利用しました。
複数の壕がモデルとされるのは、野坂本人の記憶や地元住民の証言、作品化の過程での設定変更などが理由です。
アニメ版の描写はこう違う
アニメ制作時、野坂昭如は正確な場所案内を避けました。そこで高畑勲監督は、物語や画面構成の都合から池の東岸に防空壕を描くアレンジを加えています。
| 要素 | 原作 | 証言 | アニメ版 |
|---|---|---|---|
| 親類宅 | 西宮市内 | 満池谷町付近 | 同町風の背景 |
| 防空壕 | 複数の壕 | 南側・私邸壕 | 東岸に1つ |
記念碑計画と現在
2019年、地元の郷土史家らが聞き取り調査をもとに場所を比定し、ニテコ池北の西宮震災記念碑公園に記念碑を建てる計画が報じられました。
ハルヒの巡遊の不思議マップにあるニテコ池です。
— Arc_Light (@Arc_Light1965) August 18, 2022
この池はジブリのアニメ映画「火垂るの墓」で
主人公の清太と節子が自炊生活する防空壕のある
池のモデルとなっている所です。
すぐ近くには「西宮震災記念碑公園」があり、
震災記念碑の奥に火垂るの墓のモニュメントが
建てられていました。 pic.twitter.com/YO6qFTq0gj
- 西宮震災記念碑公園
- 〒662-0022 兵庫県西宮市奥畑5−5
現在、防空壕跡は住宅地になっており、現存していません。訪れる場合は私有地やマナーに注意が必要です。
まとめ
『火垂るの墓』の舞台は、西宮市の池とその周辺にあった防空壕。実際の防空壕はもう残っていませんが、この場所には原作者の実体験が深く刻まれています。物語を知ったうえで現地の背景を知ると、作品への見方もまた変わってくるかもしれません。